
マンガ「産後うつ」


























産後うつとは?
産後うつとは、出産から数週間〜数か月程度にわたって続く、主に母親の心理的変調がみられる疾患です。家事や育児をする気力がなくなったり、極端に悲しみを感じる症状がみられます。 産後うつは、出産後のママに1~2割程度の確率で発症するといわれています。極度の悲しみや無気力を感じ、それがほぼ毎日、2週間以上続きます。特に出産を終えて日常生活に戻る産後1か月頃は、環境の変化によって産後うつを発症しやすいタイミングのため、注意が必要です。
産後うつのサイン
産後うつは、専門医によるサポートが必要なこころの病気です。放置しておくと、症状が長引いて子育てや夫婦の絆にも影響を及ぼしかねません。 まずは産後うつの症状を確認しましょう。
産後うつの主な症状
以下の症状がほぼ毎日、2週間以上続くときは産後うつを疑い、病院へ受診することをおすすめします。
- 眠れない、途中で起きてしまう
- 食欲がない、吐き気がする
- 常に憂鬱で、気分が晴れない
- 疲れる、生きる気力がない
- なぜか涙が出る
- 身体が重く、家事や仕事が片付かない
- 決断力がなく買い物に行っても決められない
男性も産後うつになる?
産後の女性のみが対象と思われがちな産後うつですが、実は男性も発症する可能性があるといわれています。国立成育医療研究センターが実施した調査では、1歳未満の子どもがいる家族のうち、メンタルヘルスに不調をきたすリスクがあった父親は全体の11%で、母親とほぼ同じ割合でした。父親の産後うつも母親同様に子どもへの影響も懸念されているため、注意が必要です。
産後うつはいつまで続く?期間は?
産後うつによる気分や体調の変化は、一般的には分娩から数週間後〜数か月かけて症状が持続します。放置すると、症状が数年間以上にわたって続いたり、悪化したりするリスクがあります。
産後うつとマタニティブルー(マタニティブルーズ)との違いは?
マタニティブルーとは
「マタニティ」という言葉から、妊娠中の症状と勘違いされがちですが、マタニティブルーは、妊娠中や出産後の女性の30~50%が経験する、自律神経やメンタルが不安定な心理状態のことをいいます。
産後うつとマタニティブルーの違い
産後うつとマタニティブルーはどちらも産後に生じる抑うつ症状ですが、産後うつは治療が必要な病気であるのに対し、マタニティブルーは自然に治っていく正常範囲内の変化という点が異なります。
マタニティブルーの場合、産後数日から2週間程度のうちに、ふいに涙が出て止まらなくなったり、いらいらしたり、落ち込んだりする等の精神症状が出現しますが、こうした感情は数日〜数週間以内に治まります。また、マタニティブルーは約3〜5割の母親が経験する感情といわれており、基本的に治療の必要はありません。
産後うつの場合、マタニティブルーよりも深刻な気分の変動があり、症状が数週間から数か月間続くため、日常生活に支障が出ます。マタニティブルーズの症状が重かったり、妊娠前、妊娠中に心の病気を経験している方は、産後うつになりやすい傾向があるといわれています。
産後うつがもたらす影響
育児への影響
親が産後うつになると、子どもとの絆をうまく築けないことがあります。そのため、ネグレクト(育児放棄)や虐待につながってしまったり、後年、子どもに情緒的・社会的・認知的な問題が生じることがあります。
夫婦関係・家族関係への影響
産後うつによる精神の不安定は、ときに夫婦・家族間の関わり合いが産前に比べてうまくいかなくなることもあります。
産後うつの原因
産後うつを発症する原因は、人によって異なり、はっきりとは解明されていません。さまざまなことが引き金となって発症に至る場合が多く、自身の身の回りの環境に何か原因がないか整理してみることで、その後の治療にもつながります。
ホルモンバランスの変化
妊娠〜出産にかけて、ママの体ではホルモンバランスの急激な変化が起き、ストレスを感じやすくなっています。そのような状態にもかかわらず、産後は疲労や育児への不安など、ストレスの種が多い時期。ホルモンバランスが急激に変化すると、ストレスに耐える脳の働きが低下し、物事をネガティブにとらえる傾向になりがちで、それが産後うつにつながりやすいといわれています。
苦しい気持ちを引き起こすきっかけ
ホルモンバランスが乱れている状態で、次の要素を抱えているときは、産後うつの発症に至りやすいとされています。
①周囲のサポートを受けにくい環境にいる
家族が遠方にいる・核家族である・パートナーが多忙であるなど、周囲のサポートを受けにくい状況は孤独感を引き起こし、産後うつ発症の原因になり得ます。 また、家庭の経済的な負担もストレスの原因になります。

②身体的ストレス
出産直後は赤ちゃんの不規則な生活リズムに合わせて授乳などのお世話をするため、睡眠不足に陥りやすく、疲労もたまりやすい状況にあります。こういった身体的ストレスが産後うつの原因となる可能性もあります。

③精神的ストレス
産後うつになりやすい性格傾向として、「生真面目」「責任感が強い」「努力家」などが挙げられます。家事・育児を完璧にこなしたい、母親としてこうありたいという気持ちが強すぎると、自分へのプレッシャーやストレスとなって負担がかかってしまうことがあります。

④本人または近親者が、うつ病の既往歴がある
本人や近親者にうつ病の既往歴がある場合は、産後うつの発症率が高くなるとされています。

このほかにも、本人がストレスに感じてしまう思い出や記憶などが発症の引き金になる場合もあります。
産後うつの治療法・対処法
産後うつかも…と思ったら、まずは受診を
産後うつは、専門医によるサポートが必要なこころの病気です。産後うつが疑われる場合は、早めにかかりつけ医や出産した産婦人科、心療内科・精神科病院等へ相談しましょう。

病院を受診することに抵抗があるときは
心療内科や精神科病院は、他の医療機関と違い、受診のハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。そんなときは、まずは身近にいるパートナーやご家族・または保健師さんや助産師さんに相談してみましょう。
もしあなたが病院を受診しなければならなくなったときも、決してひとりではありません。相談に乗ってくれた方や病院の先生たちが、あなたの味方になってくれます。
授乳中などで薬の服用に抵抗があるときは
授乳中なのに、受診して薬を服用することになったら…と、抵抗を感じる方もいるかもしれません。しかし、近年は安全な治療法が確立されてきており、薬物治療以外にも、認知行動療法等の治療法の選択肢もあります。専門家と相談しながら自分に合った方法で治療を行うことができます。
産後うつは治る?
産後うつは、適切に対処すれば数か月〜1年ほどでよくなることがほとんどとされています。本人のストレスの原因となっているものを取り除くなど、生活環境を整えることで改善することもあります。早期治療につなげるためには、パートナーをはじめとした、周りの言葉に耳を傾けることも大切。何かいつもと違う、などの変化を感じたら、先送りせずに専門家に相談してみてください。
家庭での産後うつ対処法・予防法
“無気力”は、“怠け”ではありません
産後うつの症状のひとつである「無気力感(家事・育児にやる気が出ない)」は、決して母親の怠け心が原因ではありません。ホルモンバランスの乱れなどによって、こころとからだがSOSサインを出しているのです。
休息の時間をつくる
出産後に悲しい・苦しい感情や無気力感を感じたら、できるだけすぐに休息をとるようにしましょう。 家事・育児は自分ですべてやろうと思わないようにし、パートナーや家族、または地域でサポートしてもらえるファミリーサポートやベビーシッターなどに頼り、支えてもらいましょう。 気分転換に散歩や外出をしてみたり、ゆっくりお風呂に入る時間を取ってリラックスしたりするのも効果的です。

家族が産後うつを発症したら
産後うつの発症は、本人の特性だけが原因ではありません。こころの不調も、からだの病気と変わらないという理解と受け入れが必要です。また、この病気は本人の健康だけでなく、母子関係・夫婦関係などにも影響があります。 産後うつは家族からの理解と支援が重要です。もし、産後うつについてケアの方法などに困ったときは、ご家族の方でもかかりつけ医、または地域の保健師さんや助産師さんにぜひ相談してみてください。自分たちに合ったケアの方法を一緒に考えてくれることでしょう。

- 助産師さん、保健師さん、保育士さん、栄養士さん…誰に何を相談すればいい?【保健師監修】
- 助産師さん、保健師さん、保育士さん、栄養士さん。妊娠から出産、子育てのサポートをしてくれる頼もしい専門家の方々ですが、それぞれの得意分野を知っていますか?今回は妊娠・出産・育児で悩んだとき、誰に何を…
産後のママや家族を支える取り組み
出産に伴う経済的支援
出産後は、出産手当金や 出産育児一時金などの給付を受けることができます。高額な出産費は家計を圧迫してしまいますが、これらの給付金によって経済的負担をやわらげることができます。
産後ケア事業
各市区町村が取り組む産後ケア事業では、支援を必要とするすべてのママと赤ちゃんに対して、心身のケアや育児のサポートを行うなど、産後も安心して子育てができる支援体制の確保が行われています。 実施方法はお住まいの地域により異なりますが、大きく以下の3パターンがあります。
宿泊型
- 病院や診療所に産婦さん・新生児を宿泊させ、ケアを行う
- 最長7日。分割利用も可能
※利用料金は市区町村や各施設により異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
居宅訪問(アウトリーチ)型
- 事前日程調整をし、産婦さんの自宅に支援者(助産師等の看護職や、利用者の相談内容によっては、保育士、管理栄養士、心理に関して知識のある者)が訪問し、ケアを行う。
※利用料金は市区町村や各施設により異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
通所(デイサービス)型(個別・集団)
- 保健センターなどに産婦さんが通所し、支援者がケアを行う。
- 個別と集団がある。
- 個別の場合
- 病院、診療所、助産所で居宅訪問に記載のケアの内容の全部もしくは一部を受ける。
- 集団の場合
- 複数の利用者に対して、助産師等の看護職等が保健指導、育児指導等を行う。複数の利用者がいることで、様々な情報を得ることができる。
※個別でも目的に応じてはグループワークを組み合わせて実施したり、集団でも個別相談を受けることができるなど、組み合わせは可能。
※利用料金は市区町村や各施設により異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

- 産後ケアとは?産後ケア事業や民間ケアサポートの内容をご紹介します
- 産後ケアは、出産後のママの心身をケアし、育児をサポートする取り組みです。 日本では、行政や民間企業による様々なサービスが提供されています。この記事では、代表的な産後ケア事業や民間サポートについて紹介…
その他の支援
ファミリー・サポート・センター事業
ファミリー・サポート・センター事業(通称:ファミサポ)は、各市区町村で実施されている育児サポートが受けられるサービスです。産後に休息を必要としている方など、子育て世代にとって、ファミリーサポートセンターの取り組みは育児を助けてくれる選択肢のひとつ。育児の負担が少しでも軽くなるように、上手にファミサポを活用してみましょう。

- ファミリーサポートセンターとは?利用方法やメリット・デメリットを解説【保健師監修】
- ファミリーサポートセンター(ファミサポ)とは、どのようなサービスなのでしょうか。「数時間子どもを預かってほしい」「子どもの送迎を誰かに頼みたい」と思ったとき、保育園や幼稚園、ベビーシッターサービスな…
まとめ
妊娠・出産・育児への不安は、誰にでもあります。もしも産後うつになってしまったとしても、それは不思議なことではありません。苦しい気持ちをひとりで抱え込むことは、さらに自分を追い詰めてしまいます。
産後に自分のこころとからだに異変を感じても、最初はそれを認めることに勇気がいるかもしれません。しかし、その勇気は、ご家族とママ自身が明るく幸せに過ごすための第一歩。早めに身近な人や病院等へ相談し、元気になる方法を一緒に考えていってくださいね。
-
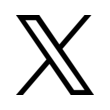 Post
Post -
 シェア
シェア -
 LINEで送る
LINEで送る



他のマンガにもコメントが届いています。
-
![「はじめての補聴器」]()
5
![さん]() あんな さん
あんな さん
-
![「初めてのおうちプール」]()
3
![さん]() チョコ🍫 さん
チョコ🍫 さん
-
![「ぼくが守りたいのは」]()
1
![さん]() チョコ さん
チョコ さん
みんなのコメントをもっとみる感動しましたこれから頑張って下さい
自分の水着に水がかかったら、叫ぶのに、お母さんには、自分出かけるのが面白いと思いました。
私もまだ子供ですが、子供が大好きなのでこの漫画を見てこの子はすごく優しい子なのかな。と思ったけど、最後、お父さんにも優しいのかなって思いましたが、お父さんだったら、守ってくれないのが、笑っちゃいました。でもただ見ててほっこりしました。☺️